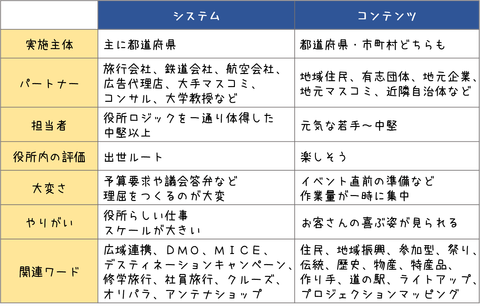ここ数年、地方公務員試験の倍率がどんどん下がってきています。
採用数が増えているためではなく、受験者数が減少しているからです。
職種によっては定員割れするケースまで生じつつあります。
以前人事院からリリースされた「国家公務員を志望者しなかった人」に対するアンケート結果によると、「採用試験の準備が大変」という理由で国家公務員を志望しなかったという人が相当数存在しています。
筆記試験対策の負担が民間就職と比べてかなり重いという意味では、地方公務員も同様です。
そのため、地方公務員の場合も、国家公務員のように「試験対策が大変だから」という理由で敬遠されていると推測されるところです。
自治体の人事課も「筆記試験負担がネックになって受験者が減っている」と考えているのか、従来の筆記試験の代わりにSPIを使うなどして、筆記試験を軽減するケースが出てきています。
ただ僕には、筆記試験を軽減するだけで志望者が増えて優秀な人材が確保できる……とは思えません。
どれだけ門戸を広げたとしても待遇は変わらない
昨今の「優秀な人材」の多くは、大手民間企業に就職しています。
地方公務員はもともと眼中にありません。
この理由は明白で、職場として魅力に乏しいからです。
給料安い、福利厚生イマイチ、やりがいが乏しい、成長できない……等々、大手民間企業と比較してしまうと、地方公務員に勝ち目はありません。
「優秀な人材」にとって、地方公務員は魅力的な職業ではないのです。
そのため、いくら筆記試験を軽減して門戸を広げたところで、「優秀な人材」が地方公務員を志望者するようになるとは到底思えません。
採用プロセス云々以前に、そもそも選択肢に入り得ないのです。
筆記試験軽減により増える層
筆記試験を軽減することで増加が見込まれる受験者層は、
- 何でもいいからとにかく公務員になりたい層
- 普通に就職活動していても役所以下の待遇しか勝ち得ない層
この2種類だと思います。
前者は、国家公務員が第一志望だった層が「筆記試験に時間を取られたくないから」と順位変更したり、「公務員になりたいけど筆記試験は嫌」という理由で警察や消防を志望していた層が路線変更したりするケースです。
後者は、これまでは主に地元中小企業に就職していたような層で、ワンチャン狙いで挑戦するタマの一つとして受験するケースです。
いずれにしても、きらびやかな経歴と実績を備えており、いろいろなところから引く手数多な、典型的な「優秀な人材」とは異なります。
こういった層のうち、面接が得意な方々が、新たに地方公務員として採用されるようになるのでしょう。
筆記特化型が消える
これまでの地方公務員採用プロセスでは、筆記試験負担が重いせいで、「筆記試験は苦手だけど面接は得意」というタイプは合格できませんでした。
面接にたどり着く前に、筆記試験で落ちてしまっていたことでしょう。
筆記試験が軽減されれば、こういうタイプの受験者が増え、かつ合格していくと思われます。
その反面、「筆記試験は得意だけど面接が苦手」というタイプは、筆記試験が軽減されると合格しづらくなるでしょう。
従来なら筆記試験で脱落していたはずの面接巧者たちと、面接という苦手なフィールドで競い合わなければいけなくなるからです。
地方公務員実務のほとんどはコミュニケーションであり、筆記試験の出来不出来はあまり関係ありません。
むしろ面接の出来不出来のほうが、実務能力に直結しているかもしれません。
そのため、「筆記試験は得意だけど面接が苦手」という層が役所から一掃されたとしても、役所運営的には差し支えないでしょう。
ただし、「筆記試験が得意」という強みを活かせなくなることで、高学歴者・高偏差値大学出身者の受験が減るのではという懸念があります。
これまでは、「筆記試験が得意であれば合格しやすい」という特徴に着目して、あえて民間企業ではなく地方公務員を志望する高学歴層・高偏差値大学出身層が一定数存在しました。
この層は読解力が非常に高く、法令や要項を一瞬で読解したり、論理的な文章を書いたり……などなど、文字ベースのコミュニケーションでは圧倒的な強みを有していて、ありがたい存在です。
筆記試験が軽減されれば、こういった層があえて地方公務員を志す理由が無くなってしまいます。
ガクチカ(もう死語か?)が貧弱でコミュ障だとしても、筆記試験さえできれば正規雇用してもらえるかもしれない……という地方公務員は、僕みたいな「ペーパーテストしか取り柄がない」勢にとっての一縷の望みです。
もし筆記試験が簡素化されてしまったら、コミュ障の就職活動は一層厳しくなるでしょう。
今となっては他人事とはいえ、僕と同類の人種が苦しむのは間違いなく、胸が痛みます。
もし筆記試験が簡素化されてしまったら、コミュ障の就職活動は一層厳しくなるでしょう。
今となっては他人事とはいえ、僕と同類の人種が苦しむのは間違いなく、胸が痛みます。
多くの自治体が思い描いている「筆記試験負担を軽減すれば受験者が増えて優秀な人材を確保できる」という展開は、民間よりも役所のほうが就職先として魅力的だという前提でないと成立しません。
この前提が成り立つかどうかは、地域ごとに異なると思います。
役所以上に魅力的な職場がたくさんある地域では、どれだけ筆記試験負担を軽減しようとも受験者はあまり増えないでしょうし、「優秀な人材」の確保はさらに難しいでしょう。
役所以上に魅力的な職場がたくさんある地域では、どれだけ筆記試験負担を軽減しようとも受験者はあまり増えないでしょうし、「優秀な人材」の確保はさらに難しいでしょう。